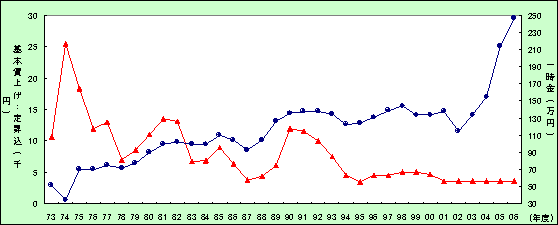同志社大学「連合寄付講座」
2006年度“働くということ-現代の労働組合”講義要録 |
■第9講(6/16)■「団体交渉と労使協議の実態」 |
||||||
|
「団体交渉と労使協議の実態」 日産労連会長 西原 浩一郎氏 |
1.日産労連の組織概要 |
全日産・一般業種労働組合連合会(以下、日産労連)は、427の企業別労働組合が加盟している労働組合であり、全国で約16万名の組合員が加入している。その中心的役割を担う日産自動車労働組合は、日産自動車の国内のすべての事業所や工場等で働く約3万名の組合員で構成されている。その他は、自動車販売会社や部品企業などの日産グループ企業の労働組合だが、電機部品企業や食品企業、文房具製造企業など、日産自動車と資本関係も取引関係もない企業の労働組合も多数加盟している。また、外数としてエルダークラブ会員が2万名加入している。これらの人々は定年退職組合員であり、各種保険等の共済制度や再就職斡旋といったサービスを日産労連から受けている。 |
2.労使協議と団体交渉に関する基本的考え方 |
(1)労使関係の基本的性格と特徴 使用者と被用者の関係は、当然ながら基本的に対立関係にある。その上で、労働組合と使用者との関係には、3つの特徴がある。1つめは、「労使相互に独立・自立・対等な関係性」であり、労使のどちらか一方が他方を支配、もしくは介入するような関係性を排除している。 2つめは、「対立と協力の並存・調和」である。「協力」は、労使共通の利益、つまり業績の向上によって企業の健全な発展を目指すために、労使が力を合わせることを意味しており、労使協議が大きな役割を果たしている。一方「対立」は、労使が協力して生み出した成果を、労使間で公正に配分するために生じる利害の対立を指し、団体交渉がその役割を担う。そして、この「協力」と「対立」という対立概念をどう併存し調和させるのかが重要であり、ある面では日本的な労使関係の基本的なエッセンスと捉えられる。例えば、労働組合が組合員の賃金の向上を意図しても、会社が収益をあげていなければ配分する原資がないため、企業と労働組合は協力して原資を稼ぐ。しかし、それを配分する際は、設備投資や株主への配当を希望する経営者と、労働条件の引き上げを希望する組合が対立するため、団体交渉により適正な配分を模索するのである。 3つめの特徴は、「基本的目標の共有」である。日産自動車の労働協約*1には、労使共通の目標として、「労使は会社の永続的な発展と、従業員の雇用の安定、及び生活の維持、向上を図る」と明記されている。 (2)労使協議と団体交渉の違い 下表は、日産労連の労使協議と団体交渉の違いを端的に表したものである。それぞれの目的と労使関係は「(1)労使関係の基本的性格と特徴」で触れているので、ここではそれ以外の項目についてみていこう。 まず、労使協議で扱われるテーマは、経営政策や企業運営上の諸問題・諸課題である。注目したいのは、労使協議で扱うこのようなテーマについて、労使間の合意が必ずしも必要ではない点である。確かに、経営者には組合の主張を最大限尊重し、労使合意に向けた誠意と努力が要請されるが、経営政策等は経営者の責任下において決定される。ただし、労使協議においても、取り扱うテーマが組合員の雇用に直接的に影響を与えるものであれば、団体交渉的な性格を帯び、労使合意が前提となる。 他方、団体交渉は、雇用や労働条件が中心的に扱われる。団体交渉では、前述したように労使合意が前提とされ、交渉の結論を必ず出すことが必要とされる。団体交渉において労使間の合意が達成されなければ争議行為に入る。すなわち、労働委員会等へ調停・斡旋を求める、あるいはストライキを実施することになる。ただし、日産労連では、争議行為は最後の手段であり、最大限話し合いの中で労使合意を結ぶことを第一義的な目標としている。ところで、日産自動車は1999年にフランスのルノー社と提携し、カルロス・ゴーン氏の下で企業再建に取り組んできたが、この提携により日産の労使関係が、以前に比べて変化したのだろうか。答えは否である。ゴーン氏が着任した際、日産労連および日産労組は、日本的な労使関係のあり方、日産における労使関係のあり方、そして日産労連の考え方について、彼と徹底的なディスカッションを行い、認識の共有化を図っている。その際、ゴーン氏は労働組合、特に日産の労使関係は尊重するという姿勢を明確にした上で、企業再建への労働組合の協力を強く求めている*2。この姿勢は、前述した日産労連の考え方と完全に合致するものであり、ルノーとの提携前後における、日産の労使協議、団体交渉のやり方も含めた全体のスキームは、全く変わらなかったのである。
*1 労働条件や団体交渉の運営等、組合活動に関して労使間で定められたルール。 |
3.日産自動車における労使関係 |
(1)団体交渉 団体交渉で特に重要なのは春の交渉、いわゆる春闘である。ここで、賃金や年間一時金(ボーナス)、労働時間短縮等の基本的労働条件に関する交渉を行っている。交渉に参加するのは、経営側が社長以下副社長クラスを中心に10名、組合側が執行部の三役を中心とする10名、そして傍聴者がそれぞれ20名で、トータル30名ずつである。要求案検討のスタートは、前年の秋ごろからであり、まず物価をはじめとするマクロ経済の動向や自動車産業の動向、日産自動車自体の企業動向等の話から始まる *3。それらに加えて、組合員の生活実態、職場の状況・課題、労働条件の他社との比較等を総合的に勘案しながら、いくつかの要求案を執行部として作り、論議を通じて一つの案に収斂していく。また、職場役員のや研修会等も順次行いながら、最終的に執行部としての要求の原案を1月下旬に職場の組合員に提案する。そして、職場ごとに組合員がその案について論議し、最終的に全組合員の挙手によって、要求が決定される。 春闘以外の団体交渉は、春闘で交渉される以外の労働条件の改定交渉が秋に行われる他、労働協約等の労使協定事項の改定交渉も順次実施される。また、最近の特徴として、ワークライフバランスや年金制度等、短期的な交渉では結論が得難いテーマが増加している。それらは、基本的には委員会で交渉が行われているが、そこで合意に至らなければ、委員会を打ち切り、団体交渉に切り替え、決着を図る。 (2)労使協議 本部・本社間の労使協議は、年2回の中央労使協議会や適宣開催される特別労使協議会、分科会で行われる。ここで特に重要なのは中央労使協議会であり、全社的な経営に関して議論している。メンバーは、経営側が社長以下副社長等10名、組合側が委員長以下役員10名であり、労働組合が事前に提出した開発、生産、販売等の各経営課題に対する質問書をもとに論議する。 また、生産、販売、海外、管理、技術、厚生といったテーマごとに開かれる分科会の中で、特に重要なのは生産分科会である。これは、毎年3月と9月に定例で開催され、生産計画や販売計画、人員体制、勤務体制といった事業や経営に関する半期ごとの計画を、労使が関係役員を中心に確認する場となっている。さらに、月ごとの変動に対応するために、毎月、月次生産協議が行われている。ここでは、翌月の生産・販売計画やその他運営上の課題等について確認している。 これらの本社と本部間の協議と連動して、支部・事業所間の事業所労使協議会や月次生産協議会、特別労使協議会がある。生産分科会に対応するのが年2回行われる事業所労使協議会であり、月次協議は支部・事業所間においても毎月行われている。 また、職場レベルでは、労使の意見交換会が適宣行われている。これは、労使協議に準ずる形で、課や部単位で毎月持たれている管理職と職場役員の話し合いである。テーマは、有給休暇の取得や職場環境の問題、上司と部下のコミュニケーションの問題等、細かいものから生産運営に関わるものまで多岐にわたる。*3 経済や産業の動向を把握するために、連合やIMF-JC(全日本金属産業労働組合協議会)の会合に参加している。 |
4.日産リバイバルプランへの対応 |
1990年代、日産車の販売シェアはグローバルレベルで継続的に下がり続け、工場の稼働率は50%強にまで落ち込んでいた。そのため、慢性的な赤字体質に陥っており、企業が存続するには、労働者にも痛みの出る抜本的な事業構造改革の断行が不可避であると認識されていた。そこで日産は、1999年3月にフランスのルノー社から資本参加を受け、ルノーとの提携の下で企業再生を果たすこととなった。 そして、99年の10月に発表された3ヵ年(2000~2002年度)の日産の再建計画が「日産リバイバルプラン」である。これは、生産や開発など9つの経営課題ごとにCFT(Cross Functional Team)というチーム *4を作り、そのチームごとに出された改善事項を集大成したものである。プランの必達目標は、00年度の連結当期利益の黒字化、02年度の売上高営業利益率4.5%の達成、並びに有利子負債総額を50%以上削減し、7,000億円以下に収めることであった。また、[1]事業の発展、[2]購買、[3]製造、[4]販売・一般管理費、[5]財務管理、[6]研究開発、[7]組織と意思決定、[8]グローバル人員体制の8つの領域から、プランは成されていた。 労働組合からすると、このプランは、当時想定していた以上に広範囲で膨大で衝撃的なものであった。労使協議の前段階で、組合が表明した考え方は、日産労組の雇用確保の3原則 *5に基づき、雇用確保が大前提であるということ、並びに、計画推進のためには、各段階において労使協議による納得と合意を必ず得ることだった。 計画の中で、特に生産工場の集約化が組合員の雇用確保に直結する問題であり、最も重要な協議項目となった。プランが公表される前の労使協議の段階では、組合は雇用や生活確保の対策が十分講じられたと判断できなかったため、以降、1年間で100回を優に超える本社・本部間の協議と職場討議を重ねた。プランが公表されると、職場は雇用や生活の不安と共に、慢性的な赤字体質の改善への期待を抱いた。しかしながら、生産がストップされる工場は、当然非難と不安の声一色に染まった。ここでは、そのような工場の一つである村山工場の例を見てみよう。 村山工場は、東京都の西部にあり、スカイラインやマーチを生産していた日産の主力工場である。工場の閉鎖に対して、そこで働く人からは、雇用や生活不安、あるいは経営責任を問う声、労働組合の対応スタンスを問う声等が沸きあがった。「日産の再生に改革は必要だが、なぜここまでやる必要があるのか、また、なぜ我々がその犠牲にならなければならないのか」という声である。労働組合は、この職場の声を起点にしながら、協議と徹底した職場との論議を重ね、3、4ヶ月後に最終的な合意形成を果たした *6。 合意に至るまでには、雇用を守るために、労働条件の方針をはっきりさせなければならなかった。当時、村山工場で働いていた人の通勤圏に工場はなかったため、移転や単身赴任など、異動条件を明確にする必要があったのである。そのため、職場から全ての要望事項を、アンケート調査によって整理した上で、会社に要求書を出し、異動に伴う特別労働条件に関わる団体交渉に入った。この中で、最高で300万円以上の特別赴任手当てや寮・社宅の完備、持ち家売却についての援助等々含め、ほぼ要求満額で決着するに至った *7。結果的に、2,100名の労働者が、栃木県と神奈川県の工場に異動した。しかしながら、どうしても異動できない約200名の労働者については、村山工場を車両部品のみを製造する工場として3年間残し、雇用を確保した。そして、その3年間の間に、200名全員の日産社内の異動も含めた条件作りを実施した。また、選択定年制度により、約500名の労働者が退職している。 このようにして、村山工場は閉鎖されたが、日産労組としては、自主的に辞職した人も含め、強制的あるいは圧力がかかる形で、意に反して日産を去る人は一人も出さなかったと自負している。その一つの証明は、村山工場が日産リバイバルプラン発表以降、01年3月の最終号車の生産まで、最高水準の品質を保ち続け、供給責任を100%果たした点にある。*4 このチームの特徴は、営業や生産、管理といった部門を越えて、部門横断的に人員を結集していることである。それにより、従来は日本でほとんど意思決定をしていたものが、日本とヨーロッパ、アメリカから若手管理職クラスを全て集め、1つ10名で構成されたチームを中心に、改善事項を集めるようになった。 |
「賃金交渉の変遷と現状」 新日鐵労連会長 神津 里季生氏 |
1.新日鐵労連の組織概要 |
新日鐵労連は、新日鐵労働組合を含む13の単位労働組合の連合体であり、組合員数は17,000名である。13の単位労組のうち、11は八幡、室蘭、釜石など事業所ごとの労働組合であり、残り2つは、新日鐵化学と新日鐵住金ステンレス *8の労組である。また、これとは別に広く連結グループの組合組織で、新日鐵グループ労組懇話会という新日鐵労連の考え方に賛同する組合員が33,000名いる *9。 新日鐵労連が直面している大きなテーマとしては、組織の拡大、連結経営への対応の強化が挙げられる。また足もとではエンジニアリング部門と新素材部門の新会社が発足しており、組合を組織することが課題である。*8 新日鐵住金ステンレスは、住友金属のステンレス部門と新日鐵のステンレス部門が統合されて2年前に設立した企業である。 |
2.新日鐵労使の話し合いの場とその特徴 |
新日鐵労連の現行協約における話し合いの場は、経営審議会、労使委員会、そして団体交渉の3つに類型化できる。まず、経営審議会は経営に関する重要事項を取り扱う話し合いの場である。この場では、組合側は意見を開陳するものの、決定権は経営側のみにあり、決定事項を会社が説明報告する。また、争議権の対象ともならない。労使委員会は、生産計画に伴う必要人員や人員の配置、あるいは、福利厚生に関する重要事項を取り扱う場である。この場では、各内容に応じて説明、報告、意見、協議を実施する。また、協議が整わなかった場合でも最終的な実施権は会社にあるが、内容に応じて争議権の対象にもなる。団体交渉は、賃金や労働時間を中心とした労働条件等の協約・協定を、協議により決定する場である。これは争議権の対象であり、話し合いによって協議が整わない限り、会社は実施できない。 そもそも、この類型が成立したのは新日鐵が発足した2年後の昭和47年であり、基本的な考え方は、今日まで引き継がれている。成立当時の考え方は、労使の対立概念をいかに生産的な方向に持っていくかであった。すなわち、法制上はいかなる労働条件の問題でも、協議が整わなくても会社は実施でき、一方、労働組合は、どのようなテーマに対しても、法制上の争議権は認められている。しかし、お互いがお互いの主張を繰り返し対立しているばかりでは、何も生まれず疲弊感だけが残るため、それぞれが何を取り、何を相手に譲るのかという考え方をまとめたものが、今日も採用されているのである。 |
3.賃金・一時金交渉結果の変遷と変化点としての現状認識 |
下図は、1973~2006年度の基本賃上げと一時金のあゆみを表したものである。これを3つの時期に区分してみると、まず第1期は、85年のプラザ合意までの高度成長時代にあたる。この時期は、ある一定のベアがあっても社員の生活向上と企業の成長が両立した時代である。第2期は、バブル期を除いた低成長・デフレ時代である。この時期は、国際競争で生き残るための人件費削減が至上命題であり、新日鐵も設備集約・労務費の削減等に伴う従業員の関連企業への出向、移籍等を経験している。ベースアップがあったとしてもわずかであり、02年、03年においては、組合としても賃上げを要求していない *10。 そして、第3期が04年度以降のポスト・ベア時代である。この時期は、一律的なベアに取り組むのではなく、「必要最小限の賃上げ原資を有効に配分するべき」と考えられている。また、それと並行して、新日鐵の春闘において、労組の主張の展開軸が決定的に変わってきている。それは、「国際競争力のある企業と魅力ある産業企業は、スパイラルアップの関係」というものである。鉄鋼産業を含む日本のものづくり産業において、国際競争力の強化は宿命である。日本でしかできない非常に品質の高いものを更に発展させる推進力がなければ、この産業は成り立たないのである。 そのようななかで、かつては、賃上げすることなど論外であり、かろうじて従業員の賃下げを回避するという事態が続いてきた。つまり、国際競争力を強化することと、労働条件を良くすることは決定的な対立概念だったのである。しかし、昨今、そして将来的な労働力不足を考慮し、組合はここ数年来、魅力ある労働条件の復活を主張している。さもなければ、有能な人材を採用できず、製品の質の向上、ひいては国際競争力の強化につながらないと考えている。このような考え方の変化の一環として、新日鐵は2006年に検証検討委員会を労使で立ち上げ、話し合いを持っている。このような場を通じて、労働組合側も問題提起を行い、賃金をはじめとする様々な制度の検討が実施されている。 基本賃上げ・一時金のあゆみ(1973年~2006年) *10 また、98年からは複数年協定がスタートしている。 |
4.労働組合としての武器は何か |
最後に、労働組合としての武器を2点挙げたい。1点目は、当然だが、労働三権としての、団結権、団体交渉権、争議権である。昭和40年代の前半以降、新日鐵労連ではストライキ権が行使されていないが、国境を越えた再編が現実のものとしてあるとき、時と場合により、相当の覚悟を持ってスト権を行使する力があることを示す必要があると考えている。2点目は、現実には最も重要な武器であるが、職場を、一人一人の力で発展させていくというマインドである。つまり、労働者側は職場を守り成果を出していき、経営側も収益の向上に努めた上で、納得的な労働条件を決定するという意識である。このような労使関係を拡大させることこそが、新日鐵を継続的に発展させる上で欠かせないのである。 |
| ▲ページトップへ |